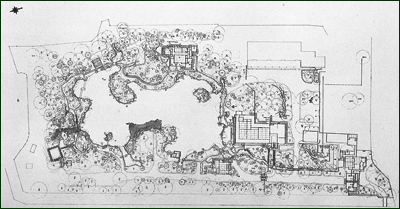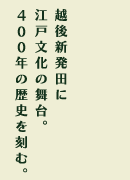原典A:「田中泰阿弥 生誕百年記念展(於・北方文化博物館/平成11年)」目録より
原典B:「孤高の庭匠 田中泰阿弥展(於・新津美術館/平成17年)」目録より
資料提供:田中泰阿弥研究会様
時空を超越した庭の匠
【著者】龍居竹之介((社)日本庭園協会会長 田中泰阿弥研究会会長)
【原典】「孤高の庭匠 田中泰阿弥展(於・新津美術館/平成17年)」目録より
〈時空を超越する〉という言葉がある。時間、空間を飛び越えることを指している。われらが泰阿弥、田中泰治を思うとき、ついこの言葉が頭に浮かぶ。
その昔、元気活発なころの泰阿弥さんは神出鬼没であった。ふらりと現れてはスッと消えて行く。書信の消印は京都以外のほうが多かった。新潟はもちろん、静岡でありあるいは東北であった。
その筆まめさは田中泰阿弥研究会が調査整理しつつある、残された書簡類の厖大さからも、何人たりと十二分に承知するところであろう。
わが家に届く書信には仕事の連絡といった実務関係が多かったが、不思議とその書面からは発信地の空気がただよった。いつも通りのちょっと癖のある独特の書体で、キリッとした文体ではあるが、いま仕事をしているこの場所は気持がよいなどと、最後の一行に記されている感懐が、その土地の香りを運んでくるのである。いま滞在しているところは、面白くないなどといった批難めいた文面は、まず無かったように思う。
つまり、いつも自分なりに心地よい場所で気分よく仕事をしていたのではなかろうか。この香りを受けとめたわが家では、「へぇ、いま山形なのか」といった調子で、その健在ぶりといつもながらの自由闊達な気風、そして滞在地の雰囲気などに思いをいたしていたのである。
そうした気性を私の父・龍居松之助は終生愛していた。新潟生れの京都育ちといった感じの泰阿弥さんには、物事にこだわらず、こせこせもしない面も強くあった。これは実際の生れや育ちとはまったく無縁の、やや江戸ッ子的な感覚でもある。一方、大和は生駒出の父親と大阪は今橋の出だった母親を持ちながら、東京で生れ育った龍居松之助は、終生、江戸ッ子を自認していたが、私などから見るとその不思議な二人の江戸ッ子ぶりには共通点があった。
金銭にこだわるところはあるのだが、表面的には無関心で恬淡としている。つまり宵越しの銭は持たないといった江戸ッ子振りを見せる。
また心底、女性が好きである。俗にいえば惚れっぽい。ひょっとすると惚れられやすいという自信にも満ちていたかも知れない。それでいて最後はいつも細君のもとに帰って納まってしまう。見得っぱりのカラ元気である。
もちろん両者の間には大同小異あるが、こうした表面的な江戸ッ子ぶりにおいては、同一であった。そして実はこれが諸国遊泳の上での原動力でもあったと思われる。
しかも泰阿弥さんは越後産のレッテルは決してはがしていない。勤勉でありかつ一つことに集中できる。俗にいえば勉強家である。京都での修業にそれが反映している。さらにそこに独立心も加わる。
故郷に錦を飾ることも忘れてはいない。その一端は銀閣寺での発掘や整備の成果が大々的に報じられることで、確かに果している。しかしその成功は逆に古庭園へののめり込みを強める結果を生む。育ての親ともいうべき銀閣寺の菅憲宗(洗月)和尚のもとを辞してまでしての“故郷への錦”は考えられない。
ここで改めて古庭園の解明と、自分なりの解釈、そこから得た技術を基本にした創意の確立に、心を決したのであろう。そしてこれは正解であった。
京都の庭匠を見ると昔から二つのタイプがある。地元で生れ育った人、これには庭匠の家に生れて自家を継承した人と、庭匠に入門した人の二種類がある。そしてもう一つが泰阿弥さんのように、地方から庭のメッカともいうべき京都をめざし、庭匠の門を叩いた人である。たとえば千葉から笈を負って入洛、植治・小川治兵衛に師事した斉藤勝雄さんも同じコースをとった有名人である。
地方出身者の中にも、修業ののち京都へ留まる人と、故郷へ戻る人と動きは多彩だが、泰阿弥さんの場合は修業後の京都暮らしは一種、いまでいえば大学院の研究生活に近かったともいえる。
生地の柏崎で培った感性、京都で得た技術のさまざまと交友関係の豊かさ、これらが大きな財産であり、それを力として突き進んだのが古きよき時代の庭の魅力の再現だった。これはやはり泰阿弥さん独自の勝手流庭づくり大学院のすばらしい研究テーマであろう。
菅和尚はじめ多くの人を知り、交友から交遊へとその間柄を深めることで、多くを広く学ぶことにもなっている。根本にあったのは間違いなく庭への情熱そのものに帰する。
第二次大戦中、社団法人日本庭園協会や日本造園士会に加わり、前者の機関紙には持論を開陳し、後者で日本造園士の称号を得てからは、気を引きしめて庭園活動に打ち込むことを誓っている。こうした団体での切磋琢磨に並々ならぬ意欲を抱いていたのであった。
同時に戦争末期から、新潟での動きが活発になった。ごくごく自然に、故郷へ錦を飾る日は訪れてきていた。そしてそれらの仕事は、戦後になって大きく花開くこととなる。
足跡を追う田中泰阿弥研究会が、いつもびっくりさせられるのは、行動範囲の広さである。記録を追いながら全国を行くのだが、それでも記録もれなどあって、突き詰めることができなかったりする。かつて、交通手段に限りのあった時代によくもこれだけ動けると感心もする。
さながら奈良時代の山岳修験者で、日本中の山々を空中飛行して往来した役行者そこのけの踏破ぶりである。そこに空間を超越した泰阿弥さんを見ることができるのだ。
長年、先代の伊藤文吉さんを待たせ続けた仕事、それはその関係する家屋敷の建築もふくめた庭づくりであった。一に北方文化博物館となった本邸であり、ついで新発田の旧溝口侯別邸の清水園である。
清水園は徳川幕府の庭方であった縣宗知が大いに肩入れした庭で、溝口家自慢の種としてよく知られるところだ。
これを整備した泰阿弥さんは、溝口以来のカラーも十分に残しながら、自分なりの考え方も加えて、伊藤さんの意に沿いつつ、古格を守った庭にしている。
北方文化博物館の場合は、それまでまったく庭らしいものが無かった屋敷に、創作した庭である。思えば母屋を中心に建物だけが点在した感じの場所は、泰阿弥さんにとっては真ッ白のカンバスだったに相違ない。
そこへ縦横無尽に彩管をふるって生みだしたのは、蓄積された技の集大成ともいうべき庭である。豪快な母屋に負けることなく、両者合わせて一幅の絵画作品に仕上げる狙い、そこから採られた指針は、自身がもっとも究めつくしたと自負していたであろう室町時代に範をとることであった。加うるに南北朝時代の雰囲気や桃山時代の面影への思いもあったと思われる。
人は北方文化博物館の庭を評して、昭和の室町の庭といったりする。「昭和」を抜かして室町の庭といっても、年々歳々、深味の増したその表情からは、おかしくはない。
泰阿弥さんは京都で学んだことをベースにして、自らの信念を出すべく創作しているのであり、その意味で、昭和の室町の庭というのは正しい。しかし、強いていえば〈昭和の田中泰阿弥の室町の庭〉と呼ぶべきだろう。
そうした感じは鶴岡の致道博物館の庭にもある。酒井侯の庭であるから、これも清水園同様、大名庭園の部類に属する。この庭を立ち直らせた泰阿弥さんは、創作とはこと変わり、丹念にその庭の訴えを受けとめている。自分の思いと庭の願いの相克を、長時間かけて解決することもあれば、一気呵成に庭を毒する禍根を容赦なく排除修整もする。その間の緩急自在も一つの手腕である。
古く伝わった庭への対処で、もっとも大事なのはその味を見きわめる目といっていい。少くとも泰阿弥さんの場合、これを複眼で見つめている。石の一つ、木の一本、飛石の一枚、それぞれが目に映るし、さらには全体像も視野にはいって、包まれた環境の中でかもし出している雰囲気もキャッチする。泰阿弥さんが整備した庭で、その仕事の跡が妙にくっきり浮き出たり、周辺となじみにくいといった例は少ない。ときには自己主張の強さを感じることもあるものの、全体のバランスを考えれば、まず許される範囲内がほとんどであろう。
一方で出身地に近い植木邸の豊耀園や、鎌倉の茶道、宗徧流家元邸などのように、その環境をいかに活用した庭にするかに腐心することもある。そこでは長い歴史を持つ庭を扱うときと異なり、その場所に即した新天地を創造しようとの意欲ものぞける。伊豆山の旅館、桃李境でも同じ動きが感じられるといっ
てよかろう。
このように泰阿弥さんの仕事は、その場に応じて、そこにふさわしいものを生みだすことを本来としている。
広い行動圏はそのまま、とり組む庭空間の多さ、大きさを示している。そしてどんな空間にも気押されや尊大さもなく、純真な心持で対応して行く。空間を飛び越す泰阿弥さんの姿が、そこにはっきりと見据えられるといって過言ではない。
いざ鎌倉ならぬ、いざ仕事となれば、泰阿弥さんの身体の中を、さまざまな時代相を持つ古典の庭の全容やディテールが、コンピューターよろしく駈けまわる。時間という枠を乗り越えての作庭テクニックの持主であればこそであろう。鎌倉時代、南北朝時代、室町時代、桃山時代、江戸時代の庭のエッセンスが泰阿弥化されて、独自の古格と新しさを享有する庭を創出する。〈時空を超越する庭の匠〉とは、泰阿弥さん以外には存在しない。

はじめに
【著者】田中泰阿弥研究会
【原典】「田中泰阿弥 生誕百年記念展(於・北方文化博物館/平成11年)」目録より
新潟県柏崎に生まれ京都に居を構えていた作庭家・田中泰阿弥。修業時代の事は詳らかではありませんが、独立して直ぐに、銀閣寺の「洗月泉石組み」の発見で銀閣寺出入りの庭師となりました。其の後も矢張り銀閣寺で「相君泉の石組み」を発見、そして発掘及び修復をし、造園界でその名を知られるようになります。以来、古庭園の発掘復元が重要な仕事の一領域を占める事となりました。
京都といえば我が国で庭の仕事をするには、もっとも理解される場所柄のように思えます。しかし、今まで判っている所では京都での作庭は僅かで、作庭する主な仕事先は新潟、東京、鎌倉等であります。資料の中に晩年の事と思われますが「…四十年も旅を続けてきて、たまに家に帰ると、テレビをつけても駄目、無暗に話しかけても駄目では、家にいない方が家人にとって良いのではと思えて…」という手紙の文面があります。四十年とは意外でしたが、まさに旅から旅の人生だったことが今更ながら思い知らされました。そんな旅の最中、歌を作り書画を描く事が楽しみの一つであったようで、数多く残されています。楽しみといえば茶道もその一つで、若い頃から修練を重ね終生お茶の世界を東京・愛苔会の仲間と共に楽しんでいました。一時は茶の世界に身を置くことも考えていた、という話を故笠原一芳氏から聞いたように記憶しています。戦争で二人の弟子を失ったことが起因しているのではないでしょうか。茶の世界といえば、泰阿弥は多くの茶室を設計しています。茶室といえば、大工は数寄屋大工という専門職となっている側面がありますが、好んで一般の大工を使った節があります。おそらく決まりきった納まりを好まなかったのでありましょう。また、使用している木材も山取りしたりで尋常ではありません。つまり、材木屋から木材を買うのではなく、山に入って立木から選ぶのです。それ故例えば、清水園の茶室を見ても、これらが昭和三十年頃に出来たものと感じないのは、この様な事が原因であるかと思われます。茶室と庭を全て一人で計画しているので、軒内というような、どちらの領域ともつかない場所の造り方が、実に巧みで、まさに泰阿弥の独壇場であります。
又、「仕事に関しては鬼の様な人だった」という話を、仕事を手伝った方から聞いた事があります。庭あるいは建築の仕事でも気に入らない所は徹底的に直させた様で、例えば、左官工事等では、黙って足で蹴って仕上げた壁を壊してしまうといった具合。現場からは次々に職人が姿を消してしまう有り様で、そんな様子も今回写真パネルで展示した庭の施主からも伺うことが出来ました。
まさに稀有な人物で、この様な人が世の中から忘れ去られてはならない。そんな思いでこの泰阿弥研究会が発足されました。当初から生誕百年に合わせて何か企画しようという目論見はありましたが、あっという間の五年間で、まだまだ道半ばですが、この度ここに生誕百年を祝う企画展を開催する事となりました。造園界の方々だけでは無く、様々な人達から御覧頂ければ幸いと思い、簡単に田中泰阿弥という人物の紹介をしてみました。

年譜
【著者】田中泰阿弥研究会
【原典】「田中泰阿弥 生誕百年記念展(於・北方文化博物館/平成11年)」目録より
| 明治31年(1898) |
0歳 |
四月二十日、新潟県刈羽郡中鯖石村大字加納笠原為治の次男として生まれる。泰治と命名 |
| 44年(1911) |
13歳 |
中鯖石尋常小学校卒業。農業の傍ら、造園技術を見習う |
| 大正1年(1912) |
14歳 |
父死亡。兄、米作が植木邸庭園を作庭する。その手伝いとして仕事場に行く |
| 3年(1914) |
16歳 |
東京の植木屋へ奉公に出る |
| 5年(1916) |
18歳 |
加納に帰り兄の手伝いをする。冬期間は埼玉県川越の酒造家へ米搗きに行く |
| 7年(1918) |
20歳 |
徴兵で高田連隊に入る。約三ヶ月で第一次世界大戦終結。兄、米作の添え書きを携えて京都岡崎の庭師「中村満次郎」方へ修業に行く |
| 8年(1919) |
21歳 |
この頃より茶道の稽古を始める |
| 10年(1921) |
23歳 |
渡り植木職人として転々とする。最後は「植治」小川治兵衛方へ |
| 14年(1925) |
27歳 |
多田宗夢より、黒谷の田中千代方への養子を請われ、田中泰治となる。 |
| 昭和元年(1926) |
28歳 |
庭師として独立する。※料亭「柳好亭」の作庭 |
| 2年(1924) |
29歳 |
銀閣寺茶席の露地作庭
京都 森田邸庭園作庭 |
| 4年(1929) |
31歳 |
結婚。京都 銀閣寺「洗月泉」の石組みを発見(九月)、その後発掘及び修復。毎月七日銀閣寺で行われる茶道の稽古に加わる。銀閣寺石組みの発掘以来、銀閣寺出入りの庭師となる。 |
| 6年(1931) |
33歳 |
京都 銀閣寺「相君泉」の石組みを発見。紅葉御殿及び西指庵に通ずる道を発見。足利義政築造といわれる茶席跡、庭園約五十坪発掘。銀閣寺の二つの石組み発掘修復に依って、その名を知られるようになる。以来、古庭園発掘復元が重要な仕事の一領域をしめる。 |
| 7年(1932) |
34歳 |
新潟県高柳 貞観園 修復 |
| 8年(1933) |
35歳 |
高柳 貞観園 修復を終える |
| 10年(1935) |
37歳 |
渡り植木職人として転々とする。最後は「植治」小川治兵衛方へ |
| 11年(1936) |
38歳 |
京都 銀閣寺鎮守石組み |
| 13年(1938) |
40歳 |
鳥取県 尾崎邸 庭園修復
※京都 岡本家粟田口別邸 庭園作庭
京都 等持院庭園復元完成
京都 天龍寺 庭園修復を始める
京都 金閣寺出入りの庭師となる |
| 15年(1940) |
42歳 |
兄、米作死亡。新潟県新発田「清水園」庭園作庭に関わるが戦争のため工事は延期
|
| 16年(1941) |
43歳 |
新潟県高柳 貞観園 石庭を作庭
※京都 西芳寺 指東庵枯山水作庭
京都 金閣寺 新設参道拡張工事 |
| 17年(1942) |
44歳 |
京都 高台寺「傘亭」 復元
京都 相国寺 庭園修復
京都 高台寺「傘亭」 復元
京都 相国寺 庭園修復
京都 金地院 庭園補修計画(二月)
京都 智積院 庭園補修計画(三月)
滋賀 蕉秀隣寺 庭園補修
※般舟院 |
| 18年(1943) |
45歳 |
京都仏教文化協会で講演を行う
演題「銀閣寺と庭園」
東京 三井邸 茶庭露地設計図
※京都 智積院 庭園補修
滋賀 福田寺 庭園補修
京都 玉林院 露地作庭 |
| 19年(1944) |
46歳 |
※東京 安田邸 庭園作庭
※東京 仙石邸 庭園作庭
鳥取 尾崎邸震災の為、復旧工事 |
| 20年(1945) |
47歳 |
東京植木株式会社に入社 |
| 23年(1948) |
50歳 |
新潟県下関 渡辺邸庭園修復を始める |
| 24年(1949) |
51歳 |
東京植木株式会社を退社 |
| 25年(1950) |
52歳 |
東京 三井邸 庭園作庭 |
| 26年(1951) |
53歳 |
文化財専門保護委員の田山方南氏より「泰阿弥」を名乗るようすすめられる
下関 渡辺邸 庭園修復完成 指定庭園申請 |
| 27年(1952) |
54歳 |
新潟県下関 渡辺邸 座敷及び茶室 完成 |
| 28年(1953) |
55歳 |
《愛苔会》この頃作られる
新潟県下関 渡辺邸 書斎前枯山水 作庭
新潟県長岡 田村邸 庭園作庭(現存せず)
熱海 桃李境 観月亭石組み終了
東京 瀬川邸 苔庭に改造
※大沢山 福寿院
※東京 竹葉亭
新潟県新発田 清水園庭園作庭を始める |
| 29年(1954) |
56歳 |
新潟県出雲崎 芭蕉苑の句碑
新潟県沢海 伊藤邸((財)北方文化博物館)
庭園作庭を始める
鎌倉 尚半亭 書院前庭作庭 |
| 30年(1955) |
57歳 |
※料亭「大和」庭園作庭(年代不詳) |
| 31年(1956) |
58歳 |
新潟県新発田 清水園 茶室工事 |
| 32年(1957) |
59歳 |
新潟県新発田 清水園 ほぼ完成(その後も手を加える) |
| 33年(1958) |
60歳 |
新潟県沢海 伊藤邸庭園完成(十月)
(財)北方文化博物館 |
| 34年(1959) |
61歳 |
新潟 大谷邸 庭園作庭
熱海 桃李境 庭園作庭
東京 瀬川邸 茶室「苔庵」完成 |
| 35年(1960) |
62歳 |
※東京 堀越邸 庭園作庭
浦和 長谷川邸 茶室及び庭園作庭(現存せず) |
| 36年(1961) |
63歳 |
東京 服部邸 庭園作庭
新潟三条 内田邸 茶室及び庭園作庭
鎌倉 瑞泉寺 茶室「南方庵」及び客殿移築
盛岡 興産相互銀行(現・北日本銀行)中庭作庭 |
| 37年(1962) |
64歳 |
新潟県三条 内田邸 庭園完成
新潟県新発田 金升酒造 庭園作庭(一部分)
東京 別宮邸 庭園作庭 |
| 38年(1963) |
65歳 |
鎌倉 長谷の大仏廻り整備、及び高徳院庭園作庭
※万満寺 茶室
鎌倉 東慶寺内 石井家墓所整備
京都 相国寺 茶室設計 |
| 39年(1964) |
66歳 |
鎌倉 長谷の大仏廻り整備、及び高徳院庭園完成
東京 坂上邸 露地作庭
東京 松本邸 茶室
新潟県出雲崎 佐藤邸 茶室及び庭園作庭 |
| 40年(1965) |
67歳 |
湯河原 鈴木邸(現・翠渓荘)庭園作庭
東京 坂上邸 石庭作庭
東京 北沢邸 庭園作庭(現存せず)
新潟県出雲崎 佐藤邸茶室及び庭園完成 |
| 41年(1966) |
68歳 |
新潟県柏崎 植木邸 庭園作庭
(以前は兄、米作に依るものであった)
※東京 猪股邸 庭園作庭
湯河原 鈴木邸庭園完成 |
| 42年(1967) |
69歳 |
新潟県柏崎 植木邸 庭園完成
植木邸の庭園は「豊耀園」と名付けられる
その完成式は泰阿弥の病気により延期された |
| 43年(1968) |
70歳 |
新潟県新発田 高澤邸(菊水酒造)庭園作庭
千葉県市川 中崎邸 庭園一部改庭 |
| 44年(1969) |
71歳 |
新潟県新発田 高澤邸 庭園完成
新潟 大谷邸 玄関前枯山水作庭
新潟県柏崎 笠原邸(本家)庭園作庭 |
| 45年(1970) |
72歳 |
京都 金閣寺 夕佳亭裏道拡張工事
鎌倉 瑞泉寺 「鶴亀の庭」作庭 |
| 46年(1971) |
73歳 |
鶴岡 致道博物館 庭園修復
鶴岡 助川邸 茶室及び露地作庭
新潟 中野邸 茶室工事 |
| 47年(1972) |
74歳 |
新潟 中野邸 茶室完成 庭園作庭
鶴岡 斉藤邸 茶室及び庭園作庭
新潟県新発田 中川邸 庭園作庭 |
| 48年(1973) |
75歳 |
※滋賀県草津 山本邸 庭園作庭
京都 金閣寺 土塀新設工事 |
| 49年(1974) |
76歳 |
新潟県新発田 清水園 書院前雨落ち及び
同仁斎に至る飛び石 |
| 50年(1975) |
77歳 |
新潟県新発田 岡仙古汲堂 庭園作庭
茨城 関邸 庭園作庭 |
| 51年(1976) |
78歳 |
鎌倉徧宗 流道場 庭園作庭 |
| 52年(1977) |
79歳 |
茨城 関邸 庭園完成 |
| 53年(1978) |
80歳 |
逝去 |

清水園を巡って
【著者】石川昇造((社)日本庭園協会・常務理事)
【原典】「田中泰阿弥 生誕百年記念展(於・北方文化博物館/平成11年)」目録より
表門より敷砂利の園路を夏木立ちの中、山鳩の鳴く声に誘われて歩を進め
ると、右手には、書院玄関とそのアプローチが目に止まります。その前に有
る流れには自然石の橋が掛けられ、その先は真の延段が凛々しい。庭門(中
門)は藤村庸軒が淀見の席の入口に建てたもので、京都から移築されたものです。それを潜ると正面には石燈籠が有り、その前を通り書院表座敷の広縁に腰を降す。ここからの眺めが唯一全望を見渡す事が出来るのです。広々とした池は草書の「水」の字を型どったものというが琵琶湖を模したのでしょうか。静かな水面に蝉時雨に閑寂な一時を………正面洲浜の奥にある滝の音を聞きながら左手に目をやると、茶席桐庵がひっそりと佇み、その先には池に浮かぶ夕佳亭、水辺には鴨が二、三、四羽、羽を休めています。又、ここ書院広縁からは、先ず礼拝石が目に止まります。名石中の名石と云われる鞍
馬石の川石で、品良く慥かな配置に、この庭園の品格を感ずるのです。縁側戸袋近くには、さりげなく「一文字」形の手水鉢が配されています。又、ここから見る木立ちの眺望は、赤松、杉、たぶ、楓、等で幽玄な雰囲気で池泉を取り囲んでいます。
さて池尻の石橋を渡り、桐庵を左手に見ながら飛石伝いに夕佳亭の方へと歩を進めます。小さな入江の石橋を渡った所が夕佳亭、やさしく、しなやかな建物が池に浮かびます。そこを過ぎると出嶋で一番の老大樹「たぶ」が有り、その下を通り洲浜へと降りて行きます。急に目の前がひらけます。池が一番大きく感じられる処です。主滝が縦に三筋となって落ちるのが良く見え、それは、奥の方に見える大きな石橋の一直線と非常に良くマッチしています。又、池の対岸には、茶室同仁斎、その右手には亀嶋の老赤松が堂々とそびえています。ここ清水園の趣は、どの場所を切り抜いても一幅の絵になるとこ
ろで、例えば、洲浜に目を落とすと、ここは桂離宮松琴亭の前にでも………否、文人画の中にでも居るような気分になります。
さて先に進みます。入江橋を渡り大きな野筋を左に右に中嶋を見ながら深山へと飛石を渡り歩を進めると、ここは主滝の上にあり深山幽谷の石組のすばらしさに、思わず言葉を忘れそうになります。………気を取り戻して沢飛石を渡り先へ行くと、先程洲浜より眺めた大きな石橋に着きます。鞍馬の自然石を中心に長尺石を八ツ橋違いに据えられており、この庭の中心であると思われます。この橋を渡ると腰掛待合が有り、ここで小休止。腰を降して天井を見上げると、この建物の妙なこと………屋根裏木小舞に細竹二本使いとし垂木は松材とし、その曲り、棯れ、斜めに渡る梁など、良く見ると頭が痛くなりそうで、どのような職人が作ったのかと考えさせられてしまいます。この待合は、同仁斎や、翠濤庵の為のもので、そちらに向うと、小さな石橋が有り、そこに佇み入江をのぞき見れば、そこには小さな滝があり、夏木立で薄暗く深い渓谷が造られています。歩を進めると、左には広い野筋の飛石が茶室へと導き、右の出嶋は、ゆったりとした起伏で、赤松と楓の林をゆっくりと足を運ぶと、同仁斎の前に辿り着きます。ここまで来て、私はいつも思うのですが、作庭家・田中泰阿弥と云う人の人柄が偲ばれるのです。というのは、同仁斎前の沓脱石ひとつ見ても、「日本刀」か「カミソリ」のようで、誰とでも妥協しない信念を見せ付けられている気がします。又、「一文字」形の手水鉢の据え方、池の汀では船着場の石組の妙、内路地の飛石、蹲踞の石組、等々、全てが自信満々なのです。「どうだ、他にこれに続けてやれる人間がおるか? 君達は、ここまで勉強しているか?」と我々に問い掛けているように思えるのです。
四時それぞれ来る度に新しい発見があり、感動を与えてくれる、そんな庭園であります。
合掌

大和民族と庭
【著者】田中泰治(泰阿弥)
【原典】「孤高の庭匠 田中泰阿弥展(於・新津美術館/平成17年)」目録より
〜大自然を描く無限の深さ〜
一生涯研究したところでなかなか得心のゆくやうな簡單なものでもない、深味と妙味を極めてゐるのが「庭」である。
何にも巨費を投じて廣大なものを造らなくても良い。唯だ一坪の「土」の上に作つた庭にも無限大の天地と共によろこびを見る庭があるのである。こゝに日本人のみがもつ「味」があり、世界無比の庭園藝術の獨特の世界が存するのである。この「庭」を單なる贅澤なることゝ普通は考へるやうだが、そんなものではない。勿論衣食住を離れたもので、それは無用の用の大なるものである。「勿體ない」といふこともこの無用の用の活用において最も發揮される考へと思ふ。
こゝで敢て云ふけれど、庭は大地に描かれたる大自然であるといふ。
あまり大きい為にその藝術價値を世人が認めようとせぬ、また理解が行かぬのである。鐘が妙音を發するやうに大自然は行脚して求める時自然そのまゝを感受するが、座して求めるにはこの造庭により求め得るのである。かやうに考へると大自然と人間の意志が合致したのが「庭」を造ることゝなるのであつて、こゝに大地の妙境が發露されまた氣高い藝術が生れるのである。
日本人が何故この「庭」といふ風光、自然に親しまねばならぬかといふこともこゝで改めて考へてみることが必要だ。それは外でもない、日本人が風光に惠まれてゐる為、この内に秀れたものを發見し、創作したのが庭として現れたのである。忠も孝も大和魂もかうした中に同じやうにこの大日本にのみ生れ出でたのである、といふことも私は考へたいのである。
〜石に美の極致を發見〜
「庭」といふ文字を見ると、大地に人の立つてゐる形であるとみたい、つまり國土のことである、この小さな庭が飛躍し活 地の相を現すと「戰の庭」となり「大東亞建設の庭」ともなるのである。戰の庭であり、決して單なる安きをのみ求める庭ではないのである。
さてこの庭には何が基本かと見るとそれは全く石である。石こそ、その中心生命であり、この石に依つて庭は成立するものであるから、この「石」について考へさせて頂くと、あの國民等しく誦する「君が代」にも「さゞれ石の巌」と奉讚申し上げるやうに不動であり、君と共に、天壤とともに不滅であるといふのがこの石によつて表れてゐる。かくの如く石は美の最極限である。
不滅の生命を現す健康に本當の美を見る如く、不滅の「石」が美の窮極を表現したものであることはあまりにも嚴かな事實である。この石に「窮極の美」を發見したのが鎌倉時代で、この時代に少くとも庭に完成した而かもそれが日本的に完成したのであるから、思想的に大きな收穫であるといへよう。そして、その思想的な確立づけをした發見者がわが夢窓國師である。
禪門の偉人、夢窓國師は自ら「疎石」といふ號まである方で、自然を愛することまことに深かつた。この夢窓國師の石を愛したる庭は、その造庭にかゝる曹源池、即ち現在の洛西天龍寺の名園がそれを代表して、今に吾々の眼前に偉大なる教訓を垂れられてゐる。この宗教上の偉人の訓へは、その生前の行藏が文字に現れてうかゞひ知るの外、この名園曹源池中に霹靂の如き獅子吼をして、今この昭和の時代にこゝに參ずるものに大示してゐる。その意をとると、とらざると、國師の獅子吼を聽くと聽かざるとはその人の唯だ自由な選擇のみ。
私はこの名園を幸に縁あつて昭和十四年、龍居先生の御指導を得て修理させて頂き、國師の偉大なる御教訓をあの池底からドロドロになつた作業服で堀り出させて頂いたのである。汗みどろで夏日の三ケ月の曹源池々底への私の修理の鍬の工作は、まことに私のみ入室を許して頂いた夢窓國師への直參の參禪行であつたと、今に私の心底に深く刻まれてゐるのである。
天龍寺の夢窓國師と庭 これは非常に深いものがある。國師は日本庭園史上に一大時期を劃した方であるが、その史的な話はまたの機會に譲つて、私は國師の造庭の眞只中に直入して御話をすゝめる事とする。
夢窓國師は洛西天龍寺の名園曹源池の前に、やはり洛西の名刹西芳寺の庭を造つてゐられるが、此西芳寺の庭と天龍寺の庭を對照すると、非常に異つた國師の御心持ちが今に窺はれるのである。これを一言にいふと、西芳寺の庭には足利尊氏の豪奢にして驕慢な心をグンと抑へる心で造られてゐることがハツキリうかゞはれるのである。而かもこの宗教の偉人は見事に尊氏をこの庭で膝に組みしいてしまつてゐるのである。そして次の天龍寺の庭を見ると全く趣きが異る。
そもそもあの不逞な尊氏も流石に 後醍醐天皇の御事をしのび奉り、その御菩提を御弔ひ申上げ奉るために造營した天龍寺は、最初から出發點が違ふのであつて、西芳寺の庭と其の趣を異にしてゐるのは當然である。
即ち夢窓國師は尊氏の請を固辭したが、どうしてもと望まれてこの寺を督して造るに至つたが、その時の尊氏は全く天皇に對する懺悔で奉仕してゐて、例へば尊氏自身がこの造營に畚をもつて勞働奉仕をしてゐる程で、幾星霜を經た今に於ても自然と西芳、天龍兩寺の庭が相異るのを感受するのも當然である。この兩者を端的に表現すると、天龍寺の庭は上下着けて端座し、眞にかしこまつて帝の靈を御弔ひ申上げてゐる感が十分に出てゐるが、一方西芳寺の庭には適正な表現かどうかは判らぬが、前にも申したやうな尊氏を押へ付けた夢窓國師といふ感であり、或は種々の御馳走を頂いた上に更に御馳走を食べて見たいといつた感があるやうにも感受させられる。
この夢窓國師の造られた天龍寺の庭も西芳寺の庭も等持院のそれも、全て夢窓國師の造られた名園には瀧があり、その瀧が全て枯れ瀧即ち實際の水を落す瀧に作つてないが、これは國師の心境に觸れる最高のものである。それは何んと表現して良いか一寸その言葉が見あたらぬが サアこれをいつて見たら水の落ちぬ瀧は無聲の瀧である。この無聲の瀧から耳を聾する那智の大飛流の轟音を聽き、或は一滴の清水の淨音に心耳をすますといふ國師の境地の發露であると申上げたいのである。
かやうに「日本の庭」は禪宗によつて完成した。その間に幾多の名匠が出で室町期となり、義政が東山に山莊「銀閣寺」を營み、東山時代の文化を創り出したが、この期は全て夢窓國師の手法とは異つたものとなつて來た。そこには「感傷」の感が表現されて來てゐる。例へば「月」などがこの「庭」に描き出されてゐて、あの東山の山莊に月待ち山の美を發現してゐる。また瀧には水が用ひられ洗月泉と稱し、中秋の名月はその瀧の眞上から涌き出させてゐる。
この時代の庭はその次の時代たる桃山期の如く豪華なものでなく、小さなところに大きな天地を見出すといふ行き方で、これが東山時代即ち義政藝術の所産であつた。義政はその生活態度に於て非常に複雑なものをもつてゐたゞけに、彼を中心として生れた諸藝術も、また種々に彼を背景に考へさせられるものがある。
それからこの義政を中心に生れた庭の藝術家、相阿彌につき一言すると、彼は勿論、東山々莊即ち銀閣の造營に參加してゐることは勿論だが、洛西龍安寺の名園即ち「虎の子渡しの庭」を造つた彼の素晴しい藝術力をうかゞはねばならぬと思ふ。前にも御話したやうに、「石」を用ひてしかもその石のもつ尊嚴性を絶對的なものとし、石より他には一木をも混へず描き出された庭園藝術は偉大なものである。殊に故事に習つて虎の親と子との親子の慈愛をあのこじんまりとした庭に見事に石のみによつて表現したのは、何んと云つても素晴しいものである。
更に洛北大徳寺塔中の大仙院の枯れ山水の如きも、相阿彌の試みた畫を立體化した新手法で、特殊な世界を生み出すに到つた。次いで桃山期に入つては、茶聖と稱せられて日本精神を一個の茶碗の底に掬み出した千利休を中心に、日本人のみが味ひ得るワビとサビの庭を述べて見ることにする。
利休を語る前に、更に一寸、桃山期の庭全體について考へて見たい。前にも述べたやうに、室町時代の造庭が北畫的主觀的とすれば、桃山期は南宋の畫風に依る客觀的作庭ともいひ得ると共に、自然の風景をそのまゝ寫し出さうとした事は、そこに飛躍をもたらしたともいへるが、同時に亦「庭」の精神を失ふ端緒ともなつた。
即ちこの期のその瀧の水の如きも、なる程水量は豐富で見る目をよろこばすやうにも見えるが、室町期の金閣寺の龍門瀑や銀閣寺の洗月泉の如き水は少量といへども石をたゝき池面に飛散するその音に聽音の妙を感じ得るが、桃山期の庭においては何の變哲もなく、どうどうと池にそゝぐのみで水音のために松風の音も聞く事の出來得ない樣な作り方をしてゐる。こんな庭に對してどうして心が澄むものか?客と話のとぎれた頃、岩を打つ金鈴の音をかすかにきく位が丁度良い。
大自然の風景は行脚に依つて感ずる大莊嚴であり、庭のたゝずまゐは靜中に動を生む源泉でなければならぬ。行脚が動的景觀であるに對し庭は靜的妙境であると考へられる。
この桃山期の庭に於ける「石組」においても誇張した個所が見られるが、それは技術の拙劣にも依るが、「石組み」の原則たる呂律の法を忘れかけた事を立證するものである。
「律」は主石を立て副石を据え、弱い所へも立添へて威儀を具足するのである。よく据つた石を律といひ、一つゞゝ二ケ所、三ケ所に其間隔を五、六寸或ひは一尺づゝ空けて切れ々々に立てるを「呂」といふのである。
吾々人間の振舞にも仁、義、禮、智、信をよくわきまへて行く人を律義者といひ、この五ツが缺けて一方のどこかへ傾いた人を「呂な人」といふ如くである。萬事に陰陽あり、生死ありこの天地の大原則を無視して何事も成り立たないと思ふ。サテ此所で造園の根本たる「石組み」の信念を申し上げてみたい。勿論この「法」も人間の作つた「法」であるから、法より入つて法を禪脱してこそ本當の法の本體が生れる。つまり無法の法が創造の根本であつて、この邊の心を得てこそはじめて法がしかも不滅の法が確立するのである。更にも一度この點を詳説して見よう。そのために左の一問一答を例に擧げることゝする。
問うて曰く、
「石に裏、表ありや否や!」
石答へて曰く、
「貴方まかせ!」
〜ワビの心と庭〜
桃山時代の庭の代表作としては、朝霧島之助作と傳へる醍醐三寳院や西本願寺對面所の虎渓の庭にその一端がうかゞへる如く、絢爛そのものである。この期、不世出の英雄、豐太閤の絢爛豪華の花も、咲く時があるからには散る秋もなければならぬ。この豐公の華かな美の極地をゆくときに、その底を流れる「あるもの」があつた。それは「死」をもなほ恐れぬマコトゴゝロ(誠心)即ちワビを大成した茶聖利休居士の妙徹境である。
桃山期の豪華な花が夕にホロホロと散る。その朝、青葉のスクスクと伸びる如く「ワビ」の精神は生ひ立つて「日本人」に生きて行つたのである。青葉の美はさることながら、今生れ出でたノビノビとしたこの青葉を指頭に感ずる時その純一無雜の味、そのなよやかさこそ誠のものであり、それそのまゝが「ワビ」なのである。
西行のものゝあわれも、世阿彌の枯木に花の咲く如き枯淡美も、芭蕉翁に見たそのまゝの世界も、マコトゴゝロの精神美を表現し得た「ワビ」に外ならぬのである。青苔日に厚うして塵おのづから無しと露路の心を喝破した利休の言葉には、何んのかざりもなく、清寂そのものである。赤松の林間を透すきらびやかな日ざしよりも、樫の葉を洩れる幽かなる日ざしを愛したのである。
樫の葉のもみぢぬからにちり積る
奥山寺の道の侘しさ
と彼はそのワビ美を發見しかつ教へた。
茶庭の露地の名稱が佛語より出てゐる以上、この關門に入るのとき、千百の妄念も飛石を踏む毎に放下し、蹲踞に心頭を灑ぎ佛心を未得底の輩は三關三庭の最後の關門たる茶室 ニヂリグチ、即ち向上關に入るを許さないといふ程の茶禪一味底の嚴肅さを、この露地即ち茶庭に於ては感じて頂き度いのである。
さうしたこの茶庭に、眞夏の茶會の涼味を盛るためにツクバヰの水に氷水を張つて茶意を得たるものとして得々然たる人があると聞いたが、水の大自然の徳を知らぬ如斯の輩のことを、もし地下に利休居士が聞いたら氷の冷味に寒心してしまふであらう。そこにはワビもサビも地に踏蹂られてゐるのだ。茶庭の飛石は歩行の易きを欲する。他の石は茶式を行ふ上に必要な石が三ツ五ツこれあるのみ、四ツ目垣のやつれを補ふ青竹の二、三本にもワビが見られ、亭主の客を敬する心が奥ゆかしく感ぜられる。苔の薄い所へ塵に深まぬ黄土、赤土を敷ならしたあたり、佗の表現した美の極致が見出せる。かくて一膝ニヂリ入つた席内こそ、教門の道場である。その席中のホノ暗さも寸時にしてホノボノと明け行く曉の空をおもはせる明暗の感覺、それこそワビ席(小間)にして得られる神祕である。
〜遠州と定信〜
江戸時代を代表する造園作家としては、どうしても小堀遠州宗甫を擧げなければならん。この遠州はまた建築家、數寄屋の作家としても當代第一の作家と言ひ度い。彼れの建築も庭も大名茶人の遠州公としての現れであり、彼れの主張精神の表現である。従つて禪に感じ得る「深さ」とか宗旦の行つた「佗」と違つて、その外觀はどこまでも垢ヌケはしてゐるけれども、その精神、味には全く貴族的な底意が溢れ出てゐるのを見出すのである。そこには徳川三百年の泰平をもたらした基礎的政策と握手したあとが十分感受し得られるのである。然しこれもこの時代の大きな流れに添つたこと、即ちその政策のための一つ流れの現れとして見たら、彼遠州の藝術も彼自身としてはどうすることも出來ぬことであつたらうと理解すべきであると共に、その時代に彼が演じた役割中に於て茶道を、ある邪道に導入した罪の何割かを彼は負はねばならぬと思ふ。
蓋し、大地に少しの無駄もなく建築と庭との連絡を一貫した方針のもとに纏め上げた、所謂數寄屋普請の大成者としての遠州の價値は大である。
この遠州の代表作として今日なほ大きな存在を示してゐるのは、洛西の桂離宮や洛東南禪寺の金地院の鶴龜の庭の如きはその典型的なものとして今に存在してゐるのである。尚この話のついでゞあるから談が飛躍するが、この時代のつゞきとしてお話しゝたいのは、文教の盛んなると共に興味あるものが生れてゐる。それは水戸光圀や松平定信のやうなすぐれた政治家であり、意圖をもつた人によつて作り出された大庭園の出現である。
つまり自己本意の庭でなくて、一般大衆の教養娯樂のために築造された庭である。この光圀や定信の生んだ庭は昭和の御代にも反映して立派に國民の精神を慰安し、明日の生命の糧をも供給するに役立つ公園の發端となつたのであつて、衆と共に生きんといふこの徳川期のすぐれた政治家の考へは實に興味あるものである。
衆と共に生きるものは強い。自己のみのために生きるものは米英の末路のそれによく見本が示めされてゐる。日本の強味は大東亞をもり立てるにあると拝聽したとき、私は庭の中からもこの大東亜聖戦の意義を拝承することが出來るやうに思ふのである。
〜大自然底の心〜
この時代の人として、光悦を語らねばならない。彼は全く大藝術家だと賞讃すべき人である。彼光悦は刀劍の目きゝを宗としてゐたといふが、彼にはその副産物として、茶碗、漆器、書畫等々何れをとつても名人の域に達したといふ、實に超人間的存在といつてよい人である。光悦の勝れた藝術は彼が刀劍に依つて徹した、鏡のやうな水のやうな一點の曇りもない銘刀の滴たる露の薫りから得た「虚心」そのものであると思ふ。私はひそかに思ふ、此の銘刀も嚴から得た鐵鑛といふ石塊を精錬に依つて生れたものであつて、私が平常取りあつかひ庭に用ひるあの石から感じ、それに内藏する素晴しい莊嚴と何等變ることがないのであると、私は常に光悦を思ふとき感ずるのである。この石が銘刀になり、庭に嚴然と大座するとき、そこに何んともいひ得ないものを感ずるのがその日本民族の特色であり、このところに美の極致を悟るのは日本人のみに許された世界だと思ふ。
話しは妙に飛び々々になるが、利休が愛した樂初代長治郎の茶碗にはあまりにも清寂を感ぜられ、光悦の生んだ茶碗にはなんとなく雄大な山をおもはせるものがある。
その色を見る時は長治郎を苔むした石と見るならば光悦は霜に濡れた落葉を想はすものがある、そのいづれをみてもそれはサビであり佗であり大なる自然であると考へたい。
私は瞑想する、この長治郎や光悦の茶碗を兩手で持ち靜かに茶を喫するときほんのりとしたそのぬくみ、むつくりとぢかに私の手の掌を通じて受けるその感觸と喫茶する私の口唇に感ずるそれは、またこれワビそのものであり、大自然に融け込むそれであり、個我雜念を忘れ大自然の淨土へ一體となりとけ込むそれであるのである。私はいつも茶を喫するときこのよろこびをよろこぶのである。宇治で若芽の茶を摘みそのまゝ乾かして粉にひき湯をそゝぎ點てゝ即ち喫す、といふ至極すなほな、少しも無理もない、何も加工もしてない茶の若芽そのまゝの味を敬つた珠光紹鴎、利休居士等、初期の茶匠たちが、かうして一碗の茶に大自然と共に生きそれと融合の妙境にあこがれ、かつこれを味得し、大自然に還元の生活をなし、さうしたところに偉大なる日本的精神美を生み出しかつ築き上げた創造を思はねばならぬ。この妙境、この世界にこそ一茶道の精神が罩められてあり、日本茶道の根源が嚴存しそこには切腹を命ぜられてもビクともせぬ大自然底の悟りがあり從容として割腹した彼利休の眞面目が露堂々と發露されてゐるのである。
大自然に生き、正しきに死すといふところに聖徳太子の仰せられた滅私奉公が少しの無理のない姿で活き、陛下の御為一死奉公といふ日本人の最高行動が實踐されるのである。
〜脈々たる氣息ある茶碗〜
この際更に茶碗の生命についても一つ語らして頂きませう、それは光悦や長治郎に限つた事ではない。高麗茶碗の井戸とか或ひはすぐれた唐津とかの雅味掬すべき茶碗をかう兩手にもつて茶を喫するときその手の感觸には確かに、明瞭に、その茶碗は息をしてゐるのである。この吾々の肉體と同じやうな脈をうつてゐるのが感ぜられるのです。まつたくこれは單なる錯覺や誇張をして申すのではない、それはあのすぐれた茶碗を手にした茶を理解する人には何人にも感じ得る感覺であり、それは明確な茶碗の氣息であり脈であることを肯定するでせう、この靈妙な感觸は全く我が日本人のみが持ち得る特殊の世界であり生命觀であると私は斷言したい。
この茶碗の脈は息は全くその茶碗作者の心が脈々と吾々「日本人」の「心」をうつのであると解せられるのである。この點を少しく明瞭に語ることを許るされるなら、
「オー長治郎さんお達者ですか?光悦さん少し怪我をしてゐるやうですが、イヤ大したことはありませんヨ」
とでもその茶碗に語りかけたい程である。もしそれ靜かな茶室にあつてその茶碗を撫する時私の胸はわくわくする程その傑れた茶碗作者、名人たちと語るなつかしみを感じる。これがすぐれた茶碗の息づかひなのである。私にはこの生きた茶碗の息づかひを感ずると同様、私の取扱ふ庭の石にも亦、この脈々たる生命感を感ずる。もしそれ靜かに心耳をすませば萬物全てしかく感ずるのである。が、ことに私の仕事即庭作りの上で取り扱ふ重要な役割をなす「水」などには多くの生命感を見るのである。いふまでもなくこの水は方圓の器に從ふ「和」の徳をもつてゐる、かうした徳を白樂天が「水は我師なり」と敬愛したのであらう。清く降る雨も葉末の露の一滴も乃至川の流れ、あの大海の潮の干滿もそこには全て生き々々としたもの、活 々地の躍動と脈々たる生命が躍つてゐる。
更に私は、私の見る自然に生命を一杯に感じて心をどるものにあの日本を表徴する靈峰富士山がある。あの富士は吾が豊葦原の不動石ではあるが、よく屡々耳にする摺鉢を伏せたやうな死物の高い山ではない。そこには否あの高く秀づる靈峰には生命の脈が波打つて盛り上つて雲表にそびゆる頂上に迄及んでゐるのである。この生きた富士こそその頭に不滅の雪をいたゞき全地球の最眞中にそびえ立つてゐるのであつて此莊嚴な相こそ眞如眞相の美の極みである。私はこの富士の靈峰を不盡の神山と稱へその壯大な莊美を談じ自然の美を仰ぐとき「人間の作つた不均整なものは空間を亂す」ものだといふことを私の造園哲學の内から生み出したのである。
〜大地を害ふなきつゝしみ〜
およそ桃山時代に發足した自然描寫的造園が江戸期に入つて因習的、圖案的な手法が加味された事が各所に見出せるがこれを概覧すると、そこには大自然的な觀念といふか、本當にこの大自然を徹見するの「心」つまり本當の審美眼がいかに缺乏したかを物語るものであつて、實に藝術的にも精神的にも悲しむべき現象だと私は敢へて言ひたいのである。
建築や他の工藝美術とは全くその理論を異にする庭に於て、その主眼とする「石」を玩弄物視して建築物の從者である位にしか考へてゐない、その作庭者の心境を思ふ時、彼等は泰平に做れて我國民の誇りであり、ことに大和魂を生んだこの我大日本の大自然を崇め尚ぶ心に弛緩が生じた反證だと極論したいのである。
私はあまり度々くり返すやうであるが、庭は大地の妙境である、土石水草木、その一物もこの人間が創つたものではない、そのそれぞれはあまりにも大きな「存在」である。かくの如きものをこゝに籍りて「神祕なる希望」を感じて人間の至醇至誠なる美感覺の極、歡喜の妙境實現の創造たる「庭」に「石」を玩弄する等、大自然を徹見する眼に堕落のあることは許すべからざることである。
私は嚴そかに思ふ、いやしくも、この大自然の石を動かし草木を移し植ゑる時、その一鍬たりともおろそかにして大地の尊嚴を してはならないと、この信念は私の造園の信念であり、無用の用たる庭藝術即ちこの大莊嚴業の意力である。
もし、それこの造園の發端は推古朝にあつて、須彌山を造る法として渡來したといふことを思ふ時、私の以上の造園信念は決して何等の誇張でも何んでもない、即ちあの小さな「庭」が大宇宙大、即ち須彌世界の大莊嚴と考へられたら一木一草を尚ぶのも當然で、大自然をいやしくもしないといふ考へ方は當然であらう。
鳥うたひ、 雲は去來す
月あり、 日あり
の至妙の世界、こゝさゝやかな庭もいさゝかな差別はない。
畏くも大御民と、日月にもつやまして御いつくしみ仰ぐ吾等國民の一人として、小庭の一隅に大東亜の建設に營々として直進する聖業を思ひ筆を擱く。

無題(抜粋)
【著者】田中泰阿弥
【原典】「田中泰阿弥 生誕百年記念展(於・北方文化博物館/平成11年)」目録より
この文章は、泰阿弥自身が清水園について書いたものを抜粋したものです。
 今回新発田市旧溝口藩の本丸あやめ城隅櫓移築工事が完成されました事は、文化の為め襟快に堪えません。私は縁あって、其の溝口藩の下屋敷(旧)清水谷御殿の庭園復元工事を北方文化博物館前館長故伊藤文吉氏に依頼されたのが昭和九年でした。それには造園界の権威、文化財保護委員である龍居松之助、同吉永義信、両氏指導のもとに、推進されたのであります。伝記に依ると、この屋敷は、面積五千余坪の平坦なる地形の南面に千余坪の池を穿ち前面に築山を築くとある。しかし、廃藩置県後家臣に寄与され、其後転売されその間に点景物や庭石の大部分は散逸し、築山の土迄売り払って酒に代えたと云うことですが貴重なものでもこうした心ない者の為めに失われていくのです。 今回新発田市旧溝口藩の本丸あやめ城隅櫓移築工事が完成されました事は、文化の為め襟快に堪えません。私は縁あって、其の溝口藩の下屋敷(旧)清水谷御殿の庭園復元工事を北方文化博物館前館長故伊藤文吉氏に依頼されたのが昭和九年でした。それには造園界の権威、文化財保護委員である龍居松之助、同吉永義信、両氏指導のもとに、推進されたのであります。伝記に依ると、この屋敷は、面積五千余坪の平坦なる地形の南面に千余坪の池を穿ち前面に築山を築くとある。しかし、廃藩置県後家臣に寄与され、其後転売されその間に点景物や庭石の大部分は散逸し、築山の土迄売り払って酒に代えたと云うことですが貴重なものでもこうした心ない者の為めに失われていくのです。
明治二十三年、先々代伊藤氏の所有するところとなり今日に及んだのであります。此の屋敷の結構がどうなっていたかは、非常に難解ではありますが、古図や古老の話を聞き、実状を調べまして、朧ろ気ながら全貌が明らかになったので、昭和十八年春着工したのであります。
この庭園復元につき特に意を強くしたことは清水御殿に参じお姫様の遊び相手を十三才までなされたという、白鳥で有名な水原町の医師家田俊一氏の曾祖母九十九歳の姥にお逢いして(この御人は、当時溝口藩家老の息女であった)結構くまなく清水御殿のおもかげを眼に見る如く聞かせていたゞいたことです。お庭は近江八景に型どって造られたので唐崎の松がたくさんの支柱にさゝえられて長い枝が水の上迄ずうと出ていました。はいかた田の浮水堂は仰しゃるとおり御殿の左側の池の岸に半分池に差しかゝっていました。それから正面築山の隅の方に積み上げた岩の上に柱が長いのやら短いのが岩の上に立つ小さいお堂の中に腰かけて源氏窓から顔を出してすぐ下の瀬田の唐橋を見ますと子供心にもほんとうにのどかで御座いました。瀬田の唐橋というのはどんな形ちで御座いましたかと聞くと、はいそれは長さが五間位御座いまして巾が三尺位でしたか低い手摺がついてまして、それがこういうふうに手ちがいになってましてお姫様と手毬つきつきわたったもんでごぜます、あんなときがもう一ぺん来ないもんかとおもてます。ほんとうにたのしごぜました。百迄生きても子供の頃が恋しいものかと考えさせられました。
池の泥揚げをした時、栗の橋杭がちゃんと残ってあることを実測致しました。巾三尺で中間で筏に組まれ長さが三十二尺あった事を識っていたので、実に正確な記憶力には舌を捲きました。築山の高さを尋ねたら、十帖の間の長押に掲げた額を指してあのくらいの高さとのお話でした、私が築いた築山が少し低いと思っていたが、あの位で好いのかとほっとしたおもい。本当に此の人は清水園復元の為めに生きていて呉れたのだと私しはおがみました。それからお茶屋のそばを水がながれてその川が八幡様のお宮の方迄ずうと続いて流れていたと仰しゃるのであるが、現状ではその風景を想起することは出来ませんが、ここにも弐神を境内に安置されたことが考えられます。
伝記によれば、この庭園は元曹洞宗の高徳寺という寺の庭であって、慶長年間溝口侯が加賀の大聖寺から入封なされて後、寺を隣村に移し、下屋敷として使用されたのでした。
また、新発田年譜、寛文八年之條では
寛文焼失ノ後御城御譜請御取掛ノ時御目見ノ間ヨリ作リ始メソレゾレ御勝手出来大書院ニテ皆出来上ル、悠庵マズ外ノ所ヲ手習ニ作リハジメテ大書院ニカカレト時ノ奉行ニ御意アリシト。御城中御膳立ノ間二間半四本立ノ板戸ハ此ノ火事ノ焼残リナル由、悠庵旧キヲ存セントノ思召ニテ大切ニ仕舞置カレシ板戸ナリ、清水谷御座敷内腰高御障子ハ元大書院ノ御障子ニテ、此ノ火事ニ焼残リシモノ今尚現存ス。因ニ清水谷御庭ハ縣宗知ヲ新発田ヘ御呼ビ下シニテ作ラセ給ヘシ由、泉水ハ草ノ水ノ字ナリ、宗知四度迄芝田ヘ下シト云。五十公野御茶屋御庭ノ泉水ハ心ノ字ナリ。法華寺ハ御意ニテ作ル、米倉村嘉兵ヱ庭モ仝人ノ作リシ由申シ傳フ。
——と記録されています。ところで文中の縣宗知を四度召して庭の修補をなさしめた縣宗知という人は、茶人系譜によると、徳川家御抱えの御庭方で、然も遠州流の流れをくむ茶匠であって今日なお宗作の歌銘、茶杓や茶碗の箱書等散見するのであります。然し今日迄の庭に関する文献及び作庭にも此の人の名前をとゞめたものを見ることが出来なかったのであるが、新発田に於て文献及び作庭が発見されたことは江戸時代の庭を考える上に非常に貴重な存在、想うに今日遠州作の庭と稱するものが各所に見られますが、流派を同じくする縣宗知等の作品も所謂遠州作として流布されたものと考えられます。私しは、この清水園の庭を修復するに当り、あく迄も先人のなした手法を踏襲せねばならないのですが、此庭内に満々と水を湛えた千余坪の池の周辺の石組も悉く石□に依って撤去され見るべき何ものもないのであります。然し新発田年譜記載の五十公野御茶屋の庭、及び米倉斉藤氏の庭が現存していることは、清水園補修の参考のみならず、造園芸術の為め重要な存在であります。特に米倉の庭は、藩候屡々此処に来遊され、また参勤交替の余次は新発田を出発され、この米倉斉藤邸が最初の休憩所であったということです。御成りの間と稱する芽葺二棟も現存し、庭中には籠付きの石が布施され、書院手水鉢等も簡略にして昔時を偲ぶに充分です。庭は狭少ながら流水式型式庭園であって築山の塵に落差一尺位の流れ瀧となって下の飄々たる大川にそゝぐのです。書院寄の渚は砂利浜となって其の隙を小さい飛石がづうと築山の方に続いています。その布石が実に其敷を極限し、要所以外には一個も無く築山の流麗なる線をより壮麗ならしめています。築山の後はすぐ田園であって遠景の連山を庭中に取り込む為め、見越の松とて五本の黒松が植えられてあったというのですが、戦時中増産の為め伐採されたとのこと、役にも立たんことを本気でせざるを得なかった当時の世相を思うとぞっとします。小松を元の位置に植えて宗知宗匠の好まれた風情がまた見られる時期が来るのだと精を込めて松の苗を植えるのでした。元禄時代に造られた庭が完全に旧軆をそのまゝ今日に傳えている庭が他にあるとは思えません。

図面(清水園の作庭図)
【原典】「田中泰阿弥 生誕百年記念展(於・北方文化博物館/平成11年)」目録より
| 
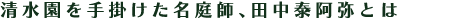


 今回新発田市旧溝口藩の本丸あやめ城隅櫓移築工事が完成されました事は、文化の為め襟快に堪えません。私は縁あって、其の溝口藩の下屋敷(旧)清水谷御殿の庭園復元工事を北方文化博物館前館長故伊藤文吉氏に依頼されたのが昭和九年でした。それには造園界の権威、文化財保護委員である龍居松之助、同吉永義信、両氏指導のもとに、推進されたのであります。伝記に依ると、この屋敷は、面積五千余坪の平坦なる地形の南面に千余坪の池を穿ち前面に築山を築くとある。しかし、廃藩置県後家臣に寄与され、其後転売されその間に点景物や庭石の大部分は散逸し、築山の土迄売り払って酒に代えたと云うことですが貴重なものでもこうした心ない者の為めに失われていくのです。
今回新発田市旧溝口藩の本丸あやめ城隅櫓移築工事が完成されました事は、文化の為め襟快に堪えません。私は縁あって、其の溝口藩の下屋敷(旧)清水谷御殿の庭園復元工事を北方文化博物館前館長故伊藤文吉氏に依頼されたのが昭和九年でした。それには造園界の権威、文化財保護委員である龍居松之助、同吉永義信、両氏指導のもとに、推進されたのであります。伝記に依ると、この屋敷は、面積五千余坪の平坦なる地形の南面に千余坪の池を穿ち前面に築山を築くとある。しかし、廃藩置県後家臣に寄与され、其後転売されその間に点景物や庭石の大部分は散逸し、築山の土迄売り払って酒に代えたと云うことですが貴重なものでもこうした心ない者の為めに失われていくのです。